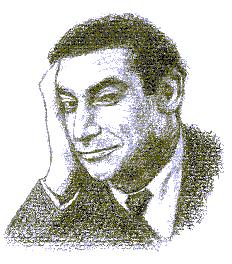
「ロバート・キャパの取材のため、ブダペストへ参ります。取材をアレンジすることをお願いすることは可能でしょうか?」会社にそんなファックスが飛び込んできたのは師走の初めのことだった。取引先からの依頼で航空券を手配したと思っていたら、おいでになるのはその身内の方で、日本で活躍されるノンフィクション作家、工藤美代子さんだという。
取材の結果は勿論、ご本人の工藤さんが書かれる本をお待ち頂くことにして、今回は、取材に辿り着くまでの珍道中をちらっとご紹介させて頂きたい。
ロバート・キャパと言えば、日本でも有名な報道写真家だ。ご存知の方も多いと思うが、本名はフリードマン・エンドレ(Friedmann Endre)。ブダペスト生れのユダヤ系ハンガリー人である。キャパという名前は、ハンガリー語の『鮫 (ツァーパ/Cápa) 』から来ていて、口の大きなキャパのニックネームだった、という説もあるが定かではない。
私も数年前に東京で開催されたロバート・キャパ展を観に行き、写真に溢れている彼の暖かい視線に、深い感動を覚えた記憶がある。会場にはハンガリー語で書かれた彼の手紙も展示されていた。
取材に先だってキャパに縁のある人物を探そうとした。とは云え、これはかなりの難問である。一九一三年生まれのキャパを知っている人がいるとしたら、九十歳は越えているだろう。兎に角キャパが通ったという学校、マダーチ・イムレ・ギムナージウム(Madách Imre Gimnázium)に電話をし、学校に残っている資料を探して貰い、資料集めに行くことにした。
マダーチ・イムレ・ギムナージウムはⅦ区、バルチャイ通り(Barcsay utca) にある、堂々たる建物の由緒ある学校で、一八八二年の設立、ハンガリーで初めての国立ギムナジウムである。当時のブダペストⅦ区にはユダヤ人が多く住んでいた。資料を見ても、キャパ在学時の全校生徒八〇三名のうち、四三、八%にあたる三五二名がユダヤ人、という記録が残っている(因みにカトリックは三五四名)。我らがエンドレは一九二三~一九三一年の八年間この学校へ通ったそうだ。
クリスマス休暇直前の学校は、どことなく楽しげな開放的な気分が漂っていた。お邪魔すると、事務所の方が思いがけない貴重な資料を用意して待っていて下さった。 何と云っても一番凄いのは、彼が最終学年、八年A組に居た頃の通知表だろう。手書きである。生年月日、住所、父親の職業(婦人服の仕立て屋)、中間・期末の成績が記入されている。まさかキャパも自分の死後五十年も経って、東洋人が自分の通信簿をコピーしに来るなんて思っても居なかっただろう。有名人とは気の毒なものである。その年の卒業生名簿もあった。そこにも全員の成績が五段階評価で記載されていた。八年A組にフリードマン・エンドレは二人居た。苗字の終わりのnが二つのFriedmannの方がキャパだ。他に、母校の同窓会へ参加した人が署名するゲスト・ブックが残っていた。貴重な資料は本当に有難かったが、残念ながら、其処から存命のキャパの知己に辿り着くことは出来なかった。通知表のコピーを頼りにキャパの住んでいたというヴァーロシュハーズ通り十番の家を捜し当て、写真を撮って帰った。
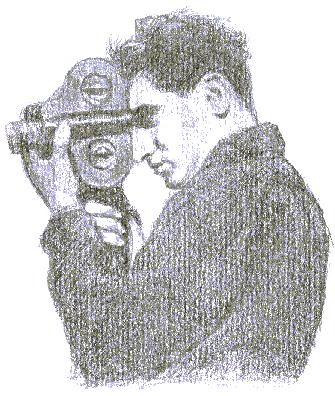
事務所に帰った私は、さて、どうすればもっとキャパに近づけるんだろうと途方に暮れ、写真家の知り合いが居たことを思い出し、彼に電話をした。「ロバート・キャパって知ってるよね?日本から作家の人が取材に来るの。マダーチ・イムレ・ギムナージウムに通っていて、ヴァーロシュハーズ通り十番に住んでいたことは、今のところ分かっているんだけど、もっと他に知る方法ないかな?」
受話器を置くと、私の隣の席にいるユーリアがおもむろに口を開いた。「リカ、私、人の電話を盗み聞きして詮索する趣味はないんだけど、云ってもいい? 今、ヴァーロシュハーズ通り十番って云ったよね? 私八年前までの四六年間その家に住んでた。」 何と云う偶然だろう。電話はしてみるものである。私は驚きと悦びのあまり、ユーリアをぴしゃぴしゃ叩き、しばし狭い事務所を踊り回った。
同僚のユーリアは、一度は定年退職したものの、家にだけ居るのがいやで、今の会社で週に数日働いている。若い頃は綺麗だったに違いない。背が高く、性格はきびきびと男っぽい。彼女の理論的且つデジタルな思考と、流れ出したら止まらない語りが、今回存分にその威力を発揮した。何せ、自分の住んでいた最上階までの階段の段数から、住んでいた部屋の高さが何メートル何センチかまで、当時アイスクリームの玉一個が幾らで、それはアパートのエレベーター二回分の運賃(有料だった!)だったことまで、正確に覚えているのである。一九一〇年生れだったというお父さんについての記憶も鮮明で、キャパの時代をある程度具体的に語れる人を私は期せずして得ることになった訳だ。
因みにこのヴァーロシュハーズ通り十番の建物は、ピルヴァックス ハーズ(Pilvax haz)と呼ばれ、地階にはピルヴァックス カフェがある。今はホテル兼レストランで、キャパ時代はおろか、ユーリア時代の面影すらとどめていないが、ピルヴァックスと云えば、一八四八年の対オーストリア独立戦争の時、ペトーフィ・シャーンドルを中心とする革命家の青年達の拠点であったという、由緒ある場所でもある。
空港に、工藤さんとご主人の加藤さんをお迎えにあがった時、私は工藤さんの短編集を読みながら二人をお待ちした。本は面白くてあっという間に読めた。文庫の中表紙に載っているお写真をちらちら見つつ、出口を見張った。
出て見えたのは本当に感じのいいご夫婦だった。工藤さんは控えめで、小柄でチャーミングな方で、私は図々しくもすっかり安心して打ち解けてしまった。ご主人の加藤さんは、画家の安野光雅さんを若く精悍に、ユーモラスにしたような素敵な方だ。長年出版社にお勤めの加藤さんと、作家の工藤さん。お二人と一緒にお話ししていると本当に楽しくて、まるで二つの巨大な本棚と歩いているような、話題と知識の宝庫だった。
コーシャ・フェレンツ氏が、ご自分の写真展を開かれるため、ケチケメートの写真博物館の館長と打ち合わせされた際、掛け合って下さったお陰で、館長とのインタビューが出来ることになった。
写真美術館はケチケメートの街中の目立たない建物の中にある。その昔、鉄道がまだ轢かれて居なかった頃、この建物は郵便馬車の宿場だった。建物は真ん中で仕切られ、片方の半分に馬が、もう片方に人が寝ていたそうだ。その後シナゴーグとして使われた時期もある。丸い天窓にはダビデの星の模様がついている。七千人も居たといわれるケチケメートのユダヤ人のうち、収容所からの生還者は約七十人。独自のシナゴーグ復旧の必然性が無くなってしまい、建物は、屠殺場として使われた後、廃墟と化した。
その建物を、自分で修復するからという条件で譲り受けたのが、現在の写真博物館である。博物館自体は国立だが、国からの援助はなく、資金は全て寄付で賄われているという。
中はモダンな内装で、小規模ながら気持ちのいい展示室があり、ありとあらゆる古いカメラや、有名な写真家の遺品、彼らのオリジナルの写真が丁寧に保存されている。これだけのものを自前で維持していくのは大変なことだ。
キンチェシュ・カーロイ館長は如何にも芸術家という雰囲気の方で、その発言や意見にこだわりが感じられた。様々な質問にもとても丁寧に応じて下さった。キャパについて出ている本は全て読んでいる、という。キャパの実弟コーネル・キャパとも会った事があり、机の脇にはコーネルの写真が飾ってあった。写真家キャパの人となりにこれだけ関心のあるハンガリー人に初めてお会いした。
以前から感じていたことだが、“母国”ハンガリーでのロバート・キャパの知名度は甚だ低い。今回訪れたマダーチ・イムレ・ギムナージウムでも、「キャパはハンガリーでも有名ですか?」という問いに対し「いや、あなた方を通して初めて知りました」という返事が返って来たほどだ。「この学校には作家のケルテース・イムレも通っていたんですよ。」とのことだったが、廊下に飾ってある、著名な卒業生の顔写真を集めた二つの額には二人の写真はなかった。二人共ユダヤ人だという歴史的背景は勿論あるが、才能と気概にずば抜けたハンガリー人は、国外で活躍の場を得、国外で評価される、というのがこの国の変わらぬ方程式なのか?と改めて思った。
館長とのインタビューの中で訳せなくて困った単語がある。「ロバート・キャパはとてもvagányな人でした。」と云われ、知らない単語に困った顔をしていると、「これは大事な単語です。キャパを語るキーワードです。」、と念を押され、益々困った。見かねた博物館のお兄さんが洪英辞典を引いて助け舟を出してくれたが、出て来た単語は「tough guy」。タフ・ガイと言われても、私の頭には、シュワルツネッガーが銃を抱えてわしわし走っているような絵が浮かんでしまい、ぴんと来ない。周りのハンガリー人に聞いて廻った結果、「大胆、向う見ずで無鉄砲」ということらしいが、ぴったり一語で言い切れる日本語を今も探している。無いのかも知れないが。
ロバート・キャパは一言で言うとこの“ヴァガーニ”な人だったのである。彼の著書『ちょっとピンぼけ(SLIGHTLY OUT OF FOCUS)』の出だしも映画のように格好いい。ニューヨーク九番街のスタジオで目を覚ますキャパ。有り金は五セント貨一枚。其処へ郵便が舞い込む。週刊誌コリアーズから特派員の仕事の依頼で、前渡金一五〇〇ドルの小切手が封入されている。が、アメリカの移民局はキャパを敵国人扱いしていて、出入国許可証はおろか、パスポートすら、ない。が、彼はあらゆるお茶目な手練手管と強運を駆使し、全ての人を見方につけて翌日にはまんまと旅券を手に入れてしまうのである。もうこれは、とんでもなく“ヴァガーニ”としか云いようがなく、格好いいのだ。
女性にももてたようだ。イングリット・バーグマン(ぞっこんだったのは彼女の方だったとか。)との恋が有名だが、戦場が変わる度、傍に居た女性も変わった、という話もある。
館長の話では、一九一三年にブダペストで生れ、一九五四年にインドシナ、ハノイ南方で地雷に散った、という二つの事実の間は、全て伝説の人だった、という。
工藤さんの本の材料を使って仕舞うといけないので、このインタビューの内容も多くは語れないが、一つ私の印象にとても残ったことがある。それは、館長が指摘した、キャパの卓越したコミュニケーション能力だ。
内乱のスペイン、日中戦争の中国大陸、北アフリカ、イタリア、そしてノルマンディ上陸、キャパの活躍の場は広い。『ちょっとピンぼけ』には、そのコミュニケーション能力を買われて急遽通訳として活躍する彼の姿、また、モザイクヨーロッパの多国語に通じ、多国人を同志として仕事をして来た彼の、瞬時に窮地を乗り切る、抜群の勘と機転についてのエピソードが尽きない。
暴露するようでキャパには申し訳ないが、国語(ハンガリー語)を含め、彼の語学科目の成績は全て中くらい。決してずば抜けた語学力の持ち主だった訳ではない。それを証明するように『ちょっとピンぼけ』には、なかなか上達せず、アクセントの抜けない彼の英語についての記述が何度か現れる。
とすると、誰もが深く心を打たれる、彼の写真に滲むあの何とも云えない暖かさ、目の前の一人一人への大きな愛情。この辺りに、彼があらゆる壁をいとも簡単に飛び越えて、人と分かり合える能力の秘密があったのだろう。
ジョン・スタインベックはキャパの写真について、こんな言葉を残している。
キャパが、―カメラとは、決して冷たいメカニックなものではない、ということを、なによりあきらかにしたことは、何人も同意するであろう。
恰も、ペンのように、カメラも使うひとによって、総てが、きめられるのだ。
それは、じかに、人間の理性と感情につながっているものである。
キャパの写真は、彼の精神の中で作られ、カメラは単に、それを完成させただけだ。
― 中略 ―
キャパの作品は、それ自体、偉大なる心の画であり、その故に、圧倒的な共感をいつも、よびおこすものである。
何人も彼にとって代わることは出来ない。すぐれた芸術家にとってかわることは、いつも、でき難いものであるが、幸いにわれわれは、少なくとも、彼の写真の中に人間の本質なるものを、学ぶことが出来るのだ。
長い引用になってしまったが、このスタインベックの名文にキャパの写真の本質が見事に言い現されているように思う。
日本にも彼の親友が居た。一九三〇年代、パリでの駈出し時代に、日本の若き芸術家たちとの、心からの交流があったようだ。一九五四年春、キャパは日本を訪れ親友と再会する。日本の風景に心底魅せられていたという。その直後、ライフ誌からの依頼で赴いたインドシナが彼の最後の戦場となった。
取材を終えてお二人を空港に見送った。大晦日の空港はのんびりとしていた。
今回の取材で新たに知ったキャパの横顔は、彼の捨て去った(または追われた)土地でのものである。この国で彼がもっと認められるように、と願いつつ、新たな時代に、彼のように国境を越えて人を愛す、第二、第三の、そして無数のキャパよ、このハンガリーの大地より出でよ! そう思った。
Papリカ
※ ノルマンディ上陸の頃のキャパを主題に映画化が決定している。オスカー賞を受賞したAdrien Brodyがキャパを演じる予定。
(パプリカ通信2004年2月号掲載)