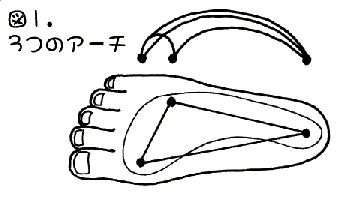
フットケアのススメ<4>
樋池 朝子
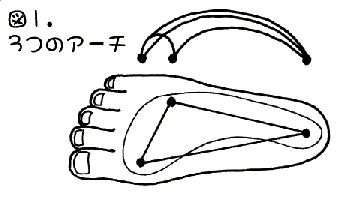
先日、「最近若者たちの間で、おしゃれな地下足袋が流行っている」という話を聞きました。お台場あたりのお店では、人気のデザインは常に品切れ状態だとか。私の住んでいる地域では、まだ地下足袋を履いている若者を見かけることはありませんが、インターネットで検索してみたら、なんともカラフルな地下足袋がたくさん売られていました。歩く場所(地面)にもよるので、一概に足によいとは言えませんが、足で地面を掴む感覚を体験できるという意味では、足のアーチのためにも、よいブームなのではないかと思います。
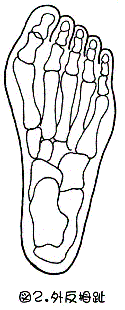
人間の足には、3つのアーチがあるのをご存知ですか? 母趾から小趾にかけての横のアーチ、母趾からにかけてのアーチ、小趾から踵(かかと)にかけてのアーチ、という3つのアーチです(図1)。母趾から踵にかけてのアーチは「土踏まず」としてよく知られていますが、「外反母趾」(図2)などのトラブルと最も関わりが深いのは、実は母趾から小趾にかけての横のアーチ。さっそく裸足になって、自分の足を見てみましょう。「え? 横のアーチなんてないぞ」と感じる人が多いのではないでしょうか。前回お話した「趾(ゆび)の力」とも関係しているのですが、合わない靴やハイヒールなどを履いているせいで、現代人の多くは、せっかくの横アーチが崩れてしまっているのです。その状態を「開張足」といいます(図3)。母趾の付け根が飛び出し、小趾側に曲がってくるという足のトラブル「外反母趾」は、この「開張足」と切っても切れない関係にあります。横のアーチが崩れた状態で、趾先の形に合っていない靴を履き続けると、外反母趾の症状がどんどん進んでしまいます。外反母趾を治すためには、手術をしなければならないと思っている人も多いようですが、足に合った靴を履き、横のアーチを形成できるように調整された中敷を使うことで、改善されるケースもたくさんあります。逆に、手術をしても開張足を改善しなければ、再発することもあるそうです。
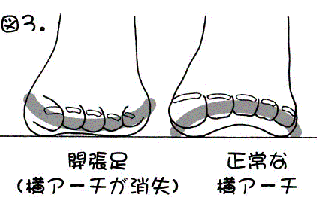
歩くときには、この3つのアーチがクッションの役割を果たし、衝撃を3点に分散させて、うまく吸収してくれます。これは、人間だけに与えられた、すばらしい構造なのです。しかし、3つのアーチの1つでも崩れてしまっていると、途端にバランスがとれなくなってしまいます。扁平足だと疲れやすかったり、開張足だと外反母趾などのトラブルが発生するのも、そのためです。そして、扁平足や開張足が増えていることは、履物と大きく関係していると考えられます。
かつて日本人は、わらじや草履のように「鼻緒」のある履物を履いていました。これは、趾の力を鍛えるにはちょうどよい履物でした。靴のように、足全体が覆われているわけではないので、趾の力を使わないと脱げてしまいます。ですから、自然と趾に力が入り、アーチを形成する筋肉や靭帯が鍛えられていたというわけです。しかし、靴を履くようになってから、人間の足は、ずいぶんと怠け者になってしまいました。趾の力を使わなくても歩けるようになると、体重を踵の方だけで支えていることが多くなります。そうなると、体が後ろに倒れないようにするために、自然と膝が曲がったり、ネコ背の姿勢になってしまうのです。さらに、足の筋肉が使われないため血行が悪くなり、冷え性やむくみなどの症状が現れたりします。何もないところで転んだりするのも、足裏のバランスの悪さが関係しているようです。
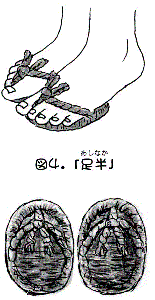
このような足裏のバランスの悪さを解消するのにピッタリな、面白い履物が、あるテレビ番組をきっかけに注目されています。それは、江戸時代の武士や農夫が実用目的や訓練のために履いていた「足半(あしなか)」(図4)という履物で、わらじを前半分だけにしたような形をしています。現在でも、鵜匠(鵜飼いで、鵜を操って魚をとらせる人)などが、濡れて滑りやすい船の上での安定感がよいという理由で、足半を履き続けているそうです。この足半は体を足の前半分で支え、しかも自然に趾を使うので、足の筋肉を鍛えつつ、足裏に集中する「メカノレセプター」を刺激します。メカノレセプターとは、足裏、特に母趾周辺部分に集中しているセンサーの働きをする器官のこと。この番組では、メカノレセプターが刺激されると、足の内側や後ろ側の筋肉が活発に働くので、足半を履き続けることで「すっきり脚」になれる…という特集をしていました。別の番組でもメカノレセプターについては取り上げられたことがあり、そのときは、車のブレーキを踏むときなどにも、メカノレセプターが重要な役割を果たしているという内容でした。足裏のアーチが崩れていると、メカノレセプターが感知する情報が不十分となり、ブレーキの踏み加減が分からなくなってしまうそうです。外反母趾などのトラブルがなく、趾を鍛えている人の方がブレーキ操作が上手く、ブレーキ操作が苦手だった人が趾を鍛える運動をしたら、前よりブレーキ操作が上手くなった、という結果が出ていました。
このように、アーチの崩れや趾を鍛えていないことが、足のトラブルはもちろん、ブレーキ操作など、意外なことに関係していることがわかってきています。便利なものが増え、足(特に趾)を使う機会も減ってしまいましたが、本当の意味で快適に過ごすためには、趾を使う機会を増やすことが必要です。若者の間で地下足袋が流行っているのも、足半が注目されているのも、「このままでは、人間の足がダメになってしまうぞ」という警告なのかもしれません。
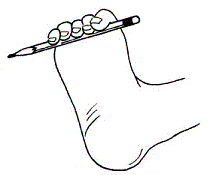
鉛筆拾いの図
■鉛筆拾い
少しお行儀が悪いですが、足を使って鉛筆を拾ってみましょう。鉛筆以外でも、タオルやビー玉など、いろんなものを、いろんな趾を使って拾ってみると、よい運動になります。
著者のHP
Salon de Peau(さろん・ど・ぽー )
http://peau.at.infoseek.co.jp
(パプリカ通信2004年6月号掲載)